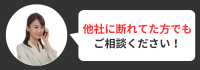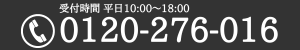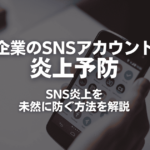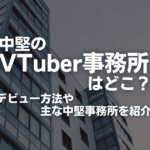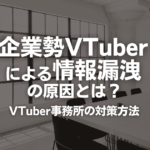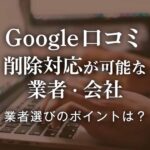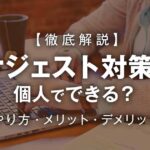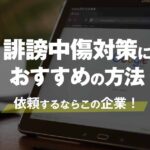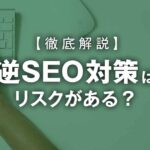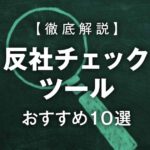「そもそも逆SEO対策の内容がイマイチわからない」
「逆SEO対策の事例が知りたい」
「逆SEO対策の具体的な方法は?」
ネット上で自社のネガティブな情報が検索結果の上位に表示され、それが風評被害や営業妨害につながっているケースがとても増えています。
そういった事実の対応法として「逆SEO対策」が挙げられます。今回は、この「逆SEO対策」の概要・事例・具体的な手法・注意すべきグレーな手法などについて解説していきます。
逆SEO対策についてよくわからないという方でもイメージが湧きやすく、すぐに実践していただける対策方法をご紹介していきますので、ぜひ参考にご覧ください。
目次
逆SEO対策の仕組みと重要性

まずはじめに、逆SEO対策の仕組みと重要性などの概要について、解説していきます。
SEO対策と逆SEO対策の違い
そもそもSEOとは「Search Engine Optimization」のそれぞれの単語の頭文字をとった言葉です。SEO対策と逆SEO対策は、両者が対象とする目的と手法に違いがあります。
SEO対策は、Webページやコンテンツを検索エンジンの検索結果で上位に表示させるための対策です。対象とするWebサイトに対し、上位表示のための工夫を施し、さまざまな調整を行います。
一方逆SEO対策は、悪質な情報・評判や、ネガティブなコンテンツなどが検索エンジンの上位に表示されることを防止するための対策です。ネガティブな情報があるサイトなどを検索エンジンから削除したり、順位を下げたりする調整を行うことで、それによる悪影響を最低限にとどめます。
逆SEO対策が必要なケース
SEO対策ではなく、逆SEO対策が必要なケースは、以下のような場合が考えられます。
ケース①ネガティブな情報・評判が拡散されている
1つ目のケースは、同業種の競合他社や悪意ある個人によって、虚偽の情報・中傷・デマ・過度に批判的な内容などが故意に拡散されている場合です。
ネガティブな情報が検索エンジンの上位に表示されると、企業や個人の評判や信頼性に深刻な悪影響を及ぼす恐れがあります。さらにネガティブな情報は、相対的に人の心に残りやすく、わずかな疑念が大きな疑念を招くなど、拡散されやすい条件が揃っています。
これらを多数の人の目に触れさせないようにするためには、ネガティブなコンテンツの検索結果順位を下げる逆SEO対策が必要となります。
ケース②不適切なコンテンツの関連付け
2つ目のケースは、企業や個人の名前が不適切なコンテンツに関連付けられている場合です。
例えば、過去に問題のあった商品が改善されているのにも関わらず、当時の問題や悪評と企業名が今だに関連付けられていたり、個人の以前の過ちが過度に強調されていることがあります。ネット上では、既に解決している問題なども残り続けてしまうのです。
これらの情報が検索結果で上位表示されると、企業・個人の評判や信頼性に誤った印象を与える可能性があります。個人名がネット上で信頼を失うと、企業の設立時にも悪影響です。
こういったケースでは、逆SEO対策によって悪質な情報の出所を明らかにし、検索結果からその情報を削除するか、影響を最小限に抑えるための対策を講じます。
ケース③不適切な画像や動画の表示
3つ目のケースは、特定のキーワードに不適切な画像や動画が関連付けられて検索結果に表示されている場合です。
真実か否かに関わらず、過去に週刊誌の編集部などのWebメディアで話題があがったことがある場合などは、自社に関わるキーワードに、不適切な画像や動画が関連付けられている場合があります。
これにより企業や個人のブランドイメージが傷ついたり、社会的な評判が損なわれる恐れがある場合は、逆SEO対策が必要です。このような複雑なケースは、個別の状況に応じて適切な対応をする必要です。
逆SEO対策の効果・実例
では、逆SEO対策を講じることで、どんな効果があるのでしょうか。実例を挙げて、解説していきます。
効果①誹謗中傷の押し下げ
逆SEO対策の効果の1つ目は、誹謗中傷の押し下げです。
誹謗中傷の押し下げの実例は、次の通りです。
企業Aで何らかの問題が発生し、インターネット上の匿名掲示板やブログ、口コミサイト、まとめサイトなどで誹謗中傷が相次ぎました。それを目にした一般消費者は「何が起きたんだろう?」とGoogleやYahooといった検索エンジンサイトで「企業A ○○(ネガティブワード)」と入力して検索行動に出ます。
例:「企業A 損失隠し」「企業A 情報漏洩」「企業A 炎上」「企業A 社長 逮捕」「企業A 本社 家宅捜査」
すると、『このキーワードの組み合わせがトレンドなのか』と学習した検索エンジンは、「企業A」と打っただけでネガティブワードを自動予測してしまい、問題発生を理解していなかった消費者にも不信感を与えてしまう結果が起こります。(これをサジェスト汚染と呼びます。)
また、こういったスキャンダルは広告収入目的で運営されているサイトや、いわゆる暴露系Youtuberといった情報発信者にとって良いネタとなり、インターネット上にコンテンツがどんどん増えていってしまう悪循環が発生します。
逆SEO対策に踏み切った企業Aは、誹謗中傷に対する釈明の実施と、リブランディングに向けてオウンドメディアの作成を開始しました。誹謗中傷コンテンツが一般消費者の目に触れないよう、ネガティブなサイトの検索順位を押し下げることに成功し、事態が収束に向かっていきました。
効果②風評被害やデマの拡散を抑制
逆SEO対策の効果の2つ目は、風評被害やデマ拡散の抑制です。
風評被害やデマ拡散の抑制の実例は、以下の通りです。
飲食店を経営している企業Bは、「期限切れの食材を使っている」という風評被害に悩まされていました。不安を感じた一般消費者は「企業B 賞味期限切れ」といったキーワードで検索行動に出るでしょう。
企業Bはこの事態を早急に把握し、自社内でどのように食材管理をしているのかといった質の高いコンテンツを作成・PRし逆SEOに成功し、消費者の不安を回復する結果に至りました。
逆SEOで対策を講じていなければ、先ほどの企業Aと同様、『企業Bは期限切れの食材を使っている』といった広告収入目的のコンテンツが検索上位を占める結果となり、風評被害がさらに拡大していたと考えられます。
近年、風評被害が発生するリスクを「レピュテーションリスク」と呼ぶようになりました。
効果③ブランディングの強化
SEO対策の効果の3つ目は、自社ブランディングの強化です。
自社ブランディングの強化の実例は、以下の通りです。
企業Cは誹謗中傷に備えて逆SEO対策を実施しました。逆SEO対策で作成したオウンドメディアやSNSによって購買チャンスが拡大し、売上がアップしました。それだけでなく、顧客とのコミュニケーションも活発化し、関係性・信頼性の構築に成功、さらには社内運営の透明性が向上し、社員のモチベーションアップ、採用時の優秀な人材確保にもつながりました。
逆SEO対策のコスト・費用と相場は?
逆SEO対策にかかるコスト・費用や相場は、こちらの記事(▶︎逆SEOっていくらかかるの?気になる費用相場や実際の対策方法を紹介)で詳細を解説しています。
初期費用の有無、月額などの定額制や成果報酬制など、料金プランもさまざまです。
上記記事を参考にして、予算を設定していきましょう。
逆SEO対策のメリットとデメリット

次に、逆SEO対策を行うメリットとデメリットについて、解説していきます。
逆SEO対策のメリット
逆SEOのメリットは、
- ネガティブな影響からビジネスを守る
- 誹謗中傷やデマの発信者と直接対立する必要がない
- 逆SEO対策をしているとバレにくい
- 売上アップにもつながる
といった点が挙げられます。
逆SEO対策では、主に自社のサイトやSNSなどを強化していくので、誹謗中傷してくる相手に対し、直接「やめてください」と言う必要がありません。誹謗中傷対策で相手を特定するには裁判所での手続きが必要になることがあったり、相手と直接やりあうことで被害がエスカレートしてしまう可能性もあります。逆SEO対策では、こういったトラブルを回避しながら誹謗中傷サイトを押し下げていきます。
また、自社のサイトや SNSが強化されることにより、売上アップにもつながります。
逆SEO対策のデメリット
逆SEOのデメリットは、
- 誹謗中傷サイトを直接削除することはできない
- 法律で裁けない
- 成果が出るまでの期間が確約できない
- ペナルティの可能性がある
といった点が挙げられます。
メリットの裏返しになりますが、投稿者やサイト運営者本人に直接連絡を行わないので、削除の依頼や法的な手続きはできません。
そして、逆SEO対策はあくまでマーケティング手法の一つなので、裁判所での手続きのように事務的に処理が進まず、日々検索順位などの数値を見ながら対策を講じていく必要があります。
逆SEO対策のリスクは、こちらの記事(▶︎逆SEO対策はリスクある?適切なネガティブサイト押し下げ方法)でも、さらに詳しく解説しています。
逆SEO対策を開始する前に必要なステップ

逆SEO対策は「ネガティブ情報のあるサイトの検索順位を下げるために行う対策」です。風評被害・誹謗中傷を防ぐためには、逆SEO対策を行う前に、ネガティブな情報を根本的に削除することができないかどうか、試みるのも1つの方法です。
ここからは、ネガティブ情報を根本的に削除するために必要なステップを解説します。
①ネガティブサイトの削除依頼
まずは、ネガティブサイトの削除依頼を行います。
サイトのお問合せフォームなどから、運営者側にネガティブな情報(サイト)自体を削除してもらうように依頼します。
サイトやページが元から削除されるので最も根本的な対策になりますが、ネガティブな情報を書き込んでいる運営者と対峙する必要があります。
連絡をとっても返答がないケースも多数あり、連絡をとること自体にハードルを感じる人も多いので、なかなか実行が難しいステップでもあります。
②Googleへの申請
運営者への削除依頼が叶わない場合、Googleに申請することで検索結果から削除してもらえる可能性があります。
例えば、そのネガティブな情報が「法律に違反している」「ユーザーの権利を侵害している」場合は、Googleの「法的な理由でコンテンツを報告する」から「リクエストを作成」し、削除の申請を行います。
この削除申請が認められれば、Googleの検索結果からは削除されます。
根本のサイトは削除されませんが、検索結果から削除されれば、多くの人の目に触れる機会は大幅に減るでしょう。
③専門家(弁護士やコンサルタント)への相談
ネガティブなサイトが複数ある場合、被害の対応などを含めて専門家(弁護士やコンサルタント)に相談することもできます。
ネット上の悪評を抑えるだけでなく、売上・集客アップ、オウンドメディア作成、SNS管理、コンテンツ最適化など、専門的な戦略が必要である場合は、専門家のコンサルティングに従って対策を行っていくことで、長期的な風評被害対策ができるでしょう。
また、名誉毀損やプライバシー侵害などの実被害があり、法的措置が必要な場合は、弁護士への相談が必要です。
逆SEO対策の具体的な方法・手段

次に、逆SEO対策の具体的な方法・手段を解説していきます。
逆SEOはテクニックが必要な対策ですが、一番大切にすべきポイントは『一般消費者に対して誠実に向き合い、信頼を得る』という正攻法につきます。
方法①信頼性の高いオリジナルコンテンツを作る
逆SEO対策の方法の1つ目は、信頼性の高いオリジナルコンテンツを作ることです。
誹謗中傷や風評被害などネガティブな情報が掲載されているサイトの順位を押し下げるため、それらのサイトに負けない信頼性の高いオリジナルコンテンツを作成し、このサイトの検索エンジン順位を上げていきます。
オリジナルコンテンツには、次のようなものがあります。
- コーポレートサイト(企業を紹介するWebサイト)
- ブランドサイト(商品やサービスを紹介するWebサイト)
- ECサイト(独自で運営する販売サイト)
- 企業ブログ(自社にかかわる情報を発信するWebサイト)
企業などが主体となって運営するこれらのWebサイトは「オウンドメディア」と総称されています。
逆SEO対策は、オウンドメディアを作り、育てていくことから始まります。
方法②SEO対策を実施する
逆SEO対策の方法の2つ目は、SEO対策を実施することです。
オリジナルコンテンツを作成後、GoogleやYahooといった検索エンジンで検索して表示されるようになるまでの期間は、早ければ投稿直後〜1週間程度、遅ければ半年〜1年以上かかることがあります。同じキーワードで作られたサイトが多ければ多いほど時間がかかる傾向にあります。
検索エンジンは図書館のようなもので、新しい本を入荷した時のように登録作業が必要になり、シンプルにその登録作業に時間がかかるからです。
そのため、クロールに備えてインデックス登録しておかなければなりません。
- クロール…インターネット上を見回りしてサイトを登録する
- インデックス登録…タイトル・見出し・コンテンツの登録
また、本を借りようと図書館にいくと、その書籍数に圧倒され、何から手をつけて良いかわからないといった経験があるかもしれません。「あなたにはこのサイトがおすすめ」と教えてくれるのが検索エンジンの役割なのですが、検索エンジン自身が「このサイトは何が書かれているのか」と把握できなければ、ユーザーにオススメできないのです。
検索エンジンに「このサイトはコレについて書いてあるよ」とわかりやすくサイトを作るのがSEO対策と言います。SEO対策を実施し、いち早く検索上位表示を目指していきます。
方法③SNSの運用を行う
逆SEO対策の方法の3つ目は、SNSの運用を行うことです。
SNSはnofollow(ノーフォロー)という属性を持つため、直接的にSEO対策とはなりませんが、逆SEO対策するにあたって大きな役割を果たします。
nofollow(ノーフォロー)とは、「リンクした側・された側で関係性を持ちません」という意味があります。つまり、SNSでいくらフォロワーを集めようとも、オウンドメディアそのもののSEO強化にはならないのです。
しかしながら、SNSには「企業のブランディング強化」「広報活動の展開」「顧客のサポートや交流」「オウンドメディアへの流入」といったメリットがある上、検索エンジンと比べて圧倒的なスピード感を持ちます。
過去には、風評被害を受けた企業が「この情報はデマです」とSNSで注意喚起し、数時間で解決した事例もあります。こういった迅速かつ真摯な対応は被害を食い止めるだけでなく、信頼アップにも繋がっていきますので、逆SEO対策の一つとして取り入れたいところです。
方法④複数の高品質サイトを作成する
逆SEO対策の方法の4つ目は、複数の高品質サイトを作成することです。
前述のような信頼性のある高品質サイトを複数作成することで、自社の風評は改善に向かいます。
なぜなら、作成したサイトが検索結果の上位に並べば、ネガティブな情報のあるサイトは、検索結果の順位から下がっていくからです。
ネガティブな情報が人の目に触れる機会が減っていくことで、徐々に風評被害も減っていくでしょう。
個人・自分で逆SEO対策を行う手法や方法とは?

個人・自分で逆SEO対策を行うには、以下の方法が必要です。
- Webサイトの制作
- SNSでの発信
- 被リンクをもらう
基本的には前述の通りですが、詳細はこちらの記事(▶︎逆SEOを個人で行う方法を大公開!ネットの悪評サイトを見えなくするには)で詳しく解説しています。
個人・自分で逆SEO対策を行うには、かなりの手間と時間がかかります。また、専門的な知識も必要で、正しく対策を講じる必要があります。なぜなら、正しい方法で逆SEO対策を行わないと、Googleからペナルティを受け、せっかく制作したWebサイトも検索結果から除外されてしまう可能性があるからです。
そういったことを防ぐためには、避けなければいけない逆SEO対策を知っておかなければいけません、グレーな逆SEO対策を次に解説していきます。
【注意】避けるべきグレーな逆SEO対策

逆SEO対策は、Google・Yahooといった検索エンジンに対して働きかける技術的手法という側面を持つため、小手先のグレーな手法が存在するのは確かです。
しかし、グレーな手法を行うとGoogleのペナルティの対象ともなるため、注意が必要です。
逆SEO対策を行う上で避けるべきグレーな手法を見ていきましょう。
①大量の低品質コピーサイトの作成
グレーな逆SEO対策の1つ目は、大量の低品質コピーサイトの作成です。
複数の高品質なWebサイトを作成することは、逆SEO対策に有効ですが、コピーサイトはシビアに判断され、低品質であると認識されます。
なぜなら、Google社はDMCA(デジタルミレニアム著作権法)を遵守しています。DMCAはWeb上のあらゆる著作物に対するアメリカの法律で、コピーサイトなど著作権に違反しているコンテンツへのアクセスを無効にすることがあります。
また、低品質なコピーサイトを大量に作成すると、検索エンジンからスパムとして認識され、サイト全体のランキングが低下する可能性があり、その回復も難しいことがあります。
②スパム的な被リンクの増加
グレーな逆SEO対策の2つ目は、スパム的な被リンクの増加です。
被リンク自体はSEO対策には有効で、むしろ被リンク数が多いほどドメインパワーが上がります。そのため、SEO対策の手段として外部サイトで被リンクをつけることもあるほどです。
しかし、検索エンジンでは「被リンクがどのようにつけられているか?」を厳しく判断しており、不自然な被リンクが多数あるサイトはペナルティの対象となってしまいます。
そのため、スパム的な被リンクを積極的に増やすのはNGです。不適切なリンクが多数ある場合は、それらを削除したり、検索エンジンに対して否認申請を行いましょう。
サイトの評価を正当に向上させるためには、正当な方法での被リンク獲得が、健全な逆SEO対策につながります。
③対象サイトへのウイルス攻撃
グレーな逆SEO対策の3つ目は、対象サイトへのウイルス攻撃です。
ウイルス攻撃は違法であり、倫理的にも誤った行為です。ウイルス攻撃は、悪意を持ったプログラムを使用して他人のコンピューターシステムに侵入し、データの破壊や盗難、システムの乗っ取りなどの被害を引き起こす行為です。
対象サイトにダメージを与えることを意図しているため、他者の利益やプライバシーを侵害する行為であり、法的に厳しく罰せられる可能性もあります。
ウイルス攻撃を行うことは、逆に自社や個人の評判を傷つける可能性があり、今後他社との信頼関係を築くことが難しくなるでしょう。
④ガイドライン違反のSEO対策の実施
グレーな逆SEO対策の4つ目は、ガイドライン違反のSEO対策の実施です。
ガイドライン違反のSEO対策は、一時的に効果を示すこともありますが、検索エンジンのアルゴリズムや規則の進化によって、サイトのランキングが低下し、最悪の場合はペナルティを受けることにつながる可能性もあります。
一般的なガイドライン違反のSEO対策は、以下の通りです。
- キーワードスタッフィング
→コンテンツ内に無理に多くのキーワードを詰め込むこと。自然な読みやすさを損ないます。 - 隠しテキストやリンク
→キーワードやテキストを隠すために、文字色を背景色と同じにしたり、CSSで非表示にしたりすること。 - ページの複製
→同じコンテンツを複数のページにコピー&ペーストすること。これはユーザーにとって価値の低いコンテンツと見なされます。
これらのガイドライン違反のSEO対策は、一時的な成果を上げることがあるかもしれませんが、長期的にはリスクが高く、信頼性や可読性の低下、検索エンジンのペナルティを招く恐れがある技術です。
逆SEO対策における注意点(Googleペナルティへの対応)

逆SEO対策は、誹謗中傷や風評被害への対策として効果的な反面、グレーな手法も存在し、正しく進めていかないとGoogleペナルティを受けてしまう可能性を含んでいます。
Googleペナルティを受けてしまうと、検索順位が大幅に下がってしまったり、検索結果表示から除外されてしまったりすることがあります。
逆SEO対策を進める中でなかなか結果が得られない場合は、Googleペナルティを受けている可能性もあります。そういった場合は、以下のことを確認してみましょう。
- 不自然な被リンク
- コピーコンテンツの掲載
- インターネット上の誹謗中傷
それでは1つずつ解説します。
注意点①不自然な被リンク
Googleペナルティを避けるために注意すべきことの1つ目は、不自然な被リンクです。
本来、被リンクは企業やサイト運営にとってプラスとなる行為ですが、不自然に貼られたリンクなどは、検索エンジンから怪しまれてしまいます。
リンクを貼るためだけに用意された低品質なサイトなどからの被リンクは、Googleペナルティの可能性が高く、サイトの評価や表示順位に悪影響を及ぼします。
注意点②コピーコンテンツの掲載
Googleペナルティを避けるために注意すべきことの2つ目は、コピーコンテンツの掲載です。
前述の通り、Google社はDMCAを遵守しているため、サイト全体のコピーだけでなく、コンテンツのコピーにも厳しいです。
次のような事例がありました。
企業Dがホームページからの検索流入減少に気づきます。「企業F」と検索してみると自社のホームページと全く同じデザインのサイトが発生しており、自社ドメインの順位が下がっていたのです。
引用や転載などの内容に関しては、コピーコンテンツではないと示す操作が必要です。コピーサイトはもちろんのこと、一部の情報を他サイトからコピーして自サイトに掲載することもNGです。
注意点③インターネット上の誹謗中傷
Googleペナルティを避けるために注意すべきことの3つ目は、インターネット上の誹謗中傷です。
ネガティブな情報に対抗する場合は、検索エンジンのガイドラインを遵守し、適切な方法を選ぶことが重要です。
インターネット上の誹謗中傷はビジネスにも悪影響を及ぼすため、グレーな手法を用いてでも自社を守ろうとしてしまいがちですが、ネット上の信頼はリアルな信頼に直結します。
ポジティブなイメージを維持するためには、不適切なコンテンツに削除依頼をする、ポジティブな情報発信の継続でドメインを強化する、適切な手法で被リンクを獲得するなど、適切な対策を行いましょう。
逆SEO対策のサポートツールとWebサービス

逆SEO対策は時間と労力を要しますが、これらの手間を省くことをサポート・支援するツールやWebサービスがありますので、以下で紹介していきます。
Webリスクモニタリングツール
逆SEO対策をサポートするツールの1つ目は、Webリスクモニタリングツールです。
Webリスクモニタリングツールには、SNSのメンションやコメントを監視する「SNSモニタリングツール」、ネット上の自社や製品・サービスに関するフィードバックを監視する「オンラインリスニングツール」など、さまざまな種類があります。
Webリスクモニタリングツールを活用すると、ネット上をリアルタイムで監視することができるため、自社に関する情報や評判を調査するのに役立ちます。逆SEO対策を講じるためには、ネット上で出回っている情報の現状を把握することが必要不可欠です。目視で調査することも可能ですが、こういったツールを利用することで過不足なく、迅速に調査することができます。
また、Webリスクモニタリングツールは、炎上のリスクなどを早期に検知することができるため、風評被害や誹謗中傷を未然に防ぐのにも有効です。
SEO対策ツール
逆SEO対策をサポートするツールの2つ目は、SEO対策ツールです。
SEO対策ツールとは、 アクセス数、コンバージョン率、検索流入キーワードなどを調査することができるツールです。「Googleアナリティクス」や「Googleサーチコンソール」などがそれに該当し、現在ではさまざまなツールが提供されています。
例えば、「Googleアナリティクス」はWebサイトのトラフィックとユーザー行動を追跡することができます。「Googleサーチコンソール」は Webサイトの検索エンジンパフォーマンスを管理するためのツールです。
これらのツールを利用することで、逆SEO対策のためのデータや情報を収集し、サイトの現状を把握することができます。
また、不適切な被リンクなども分かるので、自社のサイトの検索順位を定期的に確認できるだけでなく、逆SEO攻撃を受けているかどうかなどを調べることができます。これによって、逆SEO対策の効果を評価し、戦略の改善を行うことができます。
逆SEO対策を依頼できる専門事業者と選び方

逆SEOは、決して容易な対策ではありません。専門知識と豊富な実績を持つ専門事業者に業務を依頼することで、長期的な視野で、コスパよく対策を講じることができます。
逆SEO対策を依頼できるおすすめ専門事業者
逆SEO対策が依頼できるおすすめの専門事業者をご紹介します。
- 株式会社BLITZ Marketing
- シエンプレ株式会社
- 株式会社アクシアカンパニー
- 株式会社エルテス
- 株式会社ライフデザイン
- 株式会社ネットランド
- 株式会社エルプランニング
- 株式会社WEB広報
- 株式会社IMソリューション
- 株式会社ソルフェリオーナ
それぞれの強みなどの詳細は、こちらの記事(▶︎逆SEO対策を依頼できる業者・会社おすすめ10選を徹底比較!)で紹介しています。
逆SEO対策を依頼する専門事業者の選び方
逆SEO対策を専門事業者に依頼する場合は、以下のことに気をつけましょう。
- 料金プランに納得できるか
- 対策内容をしっかり明示してくれるか
- 同様のケースの対応実績があるか
豊富な実績と確かなノウハウを持っており、クライアントの状況をしっかりと把握し、誠意をもって対応してくれる専門事業者かどうかをしっかり検討、見極めて発注しましょう。
経過やレビューの資料共有があると、さらに安心です。
逆SEO攻撃を受けた場合の対策
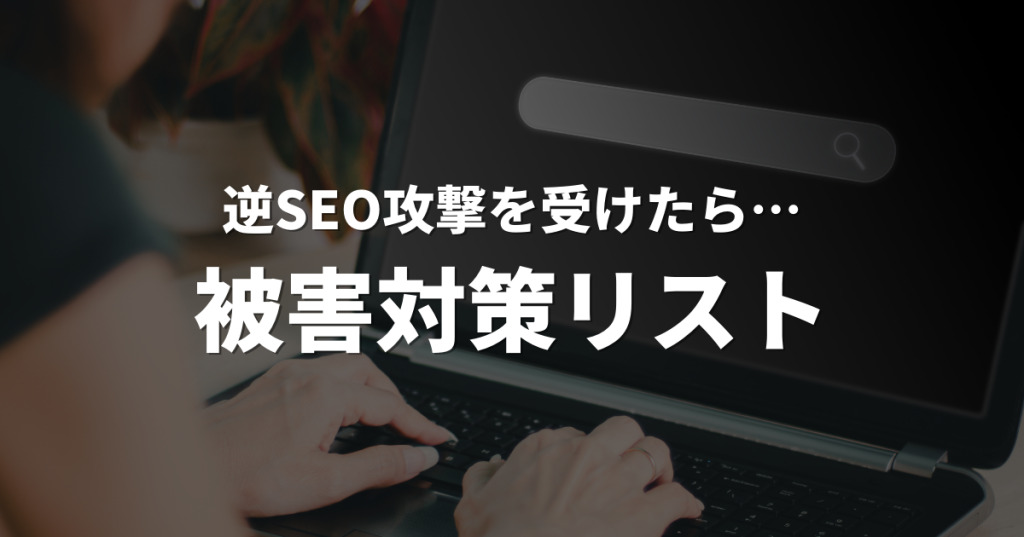
ここまで逆SEO対策について解説してきましたが、他者によって自社のオウンドメディアを対象に、逆SEOが行われるケースもあります。これにより自社サイトの「順位が落ちる」「圏外になる」といった状況を「逆SEO攻撃」と呼びます。
逆SEO対策を講じる場合は、逆SEO攻撃される可能性も視野に入れ、被害対策も同時進行させておくべきでしょう。
ここでは、逆SEO攻撃を受けた場合の対策をご紹介します。
- 自社サイトのドメインパワー強化
- 不適切な被リンクの削除依頼と否認申請の実施
- ユーザーとの接点を複数用意しておく
それでは、1つずつ見ていきましょう。
対策①自社サイトのドメインパワー強化
対策の1つ目は、自社サイトのドメインパワー強化です。
ドメインパワーの強化には、以下のような施策が有効です。一般的に「SEO対策」と呼ばれるような内容です。
- 高品質なコンテンツを提供する
- キーワードリサーチと最適化
- 内部リンク構造の最適化
- ページ速度の最適化
- 定期的なコンテンツ更新
ドメインパワーを強化しておくと、逆SEO攻撃を受けたとしても、検索結果の上位を簡単に奪われることはありません。
対策②不適切な被リンクの削除と否認
対策の2つ目は、不適切な被リンクの削除と否認です。
不適切な被リンクがあるとサイトの評価やランキングに悪影響を及ぼすため、適切な対処が必要です。
リンクされているサイトは、GoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールから確認できます。不適切な被リンクがある場合は、リンク元のWebサイトの管理者に連絡するための方法を取得します。さらにリンクのURLや削除理由などを記載し、管理者に削除依頼をします。
それと同時に、Googleなどの検索エンジンに対し、否認申請を行います。否認申請が認められると、特定の被リンクが自身のWebサイトに影響を与えないようにすることができます。
否認申請する時は、そのリンクが自身のコントロール外であることを示す情報や根拠を示します。否認申請を受け付けたら、Googleなどの検索エンジンは審査を行います。申請が承認されれば、そのリンクは評価から除外されることになります。
対策③ユーザーとの接点を複数用意しておく
対策の3つ目は、ユーザーとの接点を複数用意しておくことです。
逆SEO攻撃を受け、万が一自社サイトの検索結果順位が下がってしまうと、いつも検索エンジンからサイトやサービスを利用していたユーザーがたどり着けない可能性があります。
また、誹謗中傷やデマの拡散について、企業からの正式な見解を待つユーザーも多いでしょう。
検索エンジンからの検索流入だけでなく、TwitterやInstagram、メールマガジン、LINE公式アカウントなど、ユーザーとの接点を複数持っておけば、スピーディに対策が打てます。
「正しい情報を発信できる場を複数持っておく」ことは、逆SEOを行う上で重視すべき対策の1つです。
逆SEO対策の成功への道は、課題の解決と成果の達成
この記事では「逆SEO対策」の概要・事例・具体的な手法・注意すべきグレーな手法などについて、詳しく解説しました。
逆SEO対策の成功への道は、オウンドメディア構築やSNS運用といったデジタル面の「攻め」の対策と、検索順位の維持や被リンクの監視といった「守り」の対策を同時進行させていくのがポイントです。
また、ネガティブな情報を特定して「課題の解決」と、ネット上のポジティブな評価を得る「成果の達成」をしっかりと確認しながら行なっていくことが重要です。
一方で、短期間の逆SEO対策は決して完全な対策ではなく、長期にわたる持続的な取り組みが必要です。
成果を維持するためには定期的なコンテンツ更新などを中心に、オンライン上の信頼を着実に積み上げ、最大に強化していくことが不可欠になっていくでしょう。
【無料】風評被害対策の相談はBLITZ Marketingへ!
ネガティブなコンテンツの検索順位を押し下げる逆SEO対策ですが、手間と時間が必要で、検索エンジンのアルゴリズムは日々進化しているため、専門知識も不可欠です。
グレーな手法も存在しているため、ペナルティを受けないような正攻法で進めることが重要です。
そのため、逆SEO対策は実績豊富プロに依頼することをおすすめします。
創業10年以上にわたり、風評被害・誹謗中傷対策を展開しているBLITZ Marketing(ブリッツマーケティング)は、お客様それぞれのお悩みにあった対策をご提案し、ネット上の悪質な被害を業界一早く解決しています。
正しい逆SEO対策を行うことで、集客・売上アップにもつながり、悪質な誹謗中傷や風評被害から自社を遠ざける体制を作り上げることができます!相談・お見積もりは無料です。
弊社は風評被害・誹謗中傷対策をはじめ、Webマーケティングサービスを各種用意しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

- 誹謗中傷対策とWebマーケティングに精通した専門家です。デジタルリスク対策の実績を持ち、これまでに1,000社を超えるクライアントのWebブランディング課題を解決してきました。豊富な経験と専門知識を活かし、クライアントのビジネス成功に貢献しています。
最新の投稿
 SNS対策2025年7月3日企業のSNSアカウント炎上予防|SNS炎上を未然に防ぐ方法を解説
SNS対策2025年7月3日企業のSNSアカウント炎上予防|SNS炎上を未然に防ぐ方法を解説 ブランディング2025年6月27日中堅のVTuber事務所はどこ?デビュー方法や主な中堅事務所を紹介
ブランディング2025年6月27日中堅のVTuber事務所はどこ?デビュー方法や主な中堅事務所を紹介 誹謗中傷対策2025年6月18日有名な個人勢VTuberを紹介|成功している人の特徴や人気の秘密も解説
誹謗中傷対策2025年6月18日有名な個人勢VTuberを紹介|成功している人の特徴や人気の秘密も解説 コンプライアンス2025年6月18日企業勢VTuberによる情報漏洩の原因とは?VTuber事務所の対策方法
コンプライアンス2025年6月18日企業勢VTuberによる情報漏洩の原因とは?VTuber事務所の対策方法
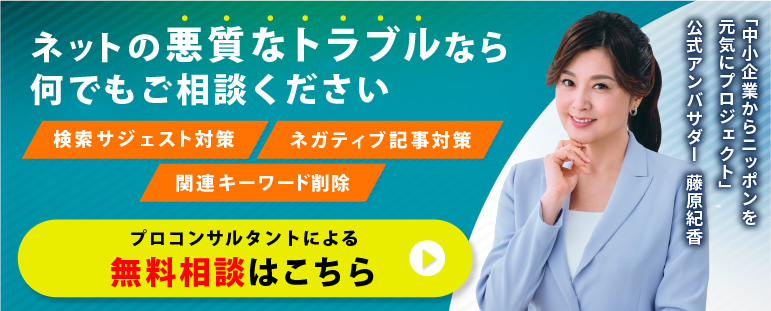
\ かんたん30秒で無料相談 /
お問い合わせはこちら