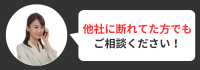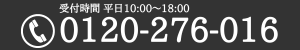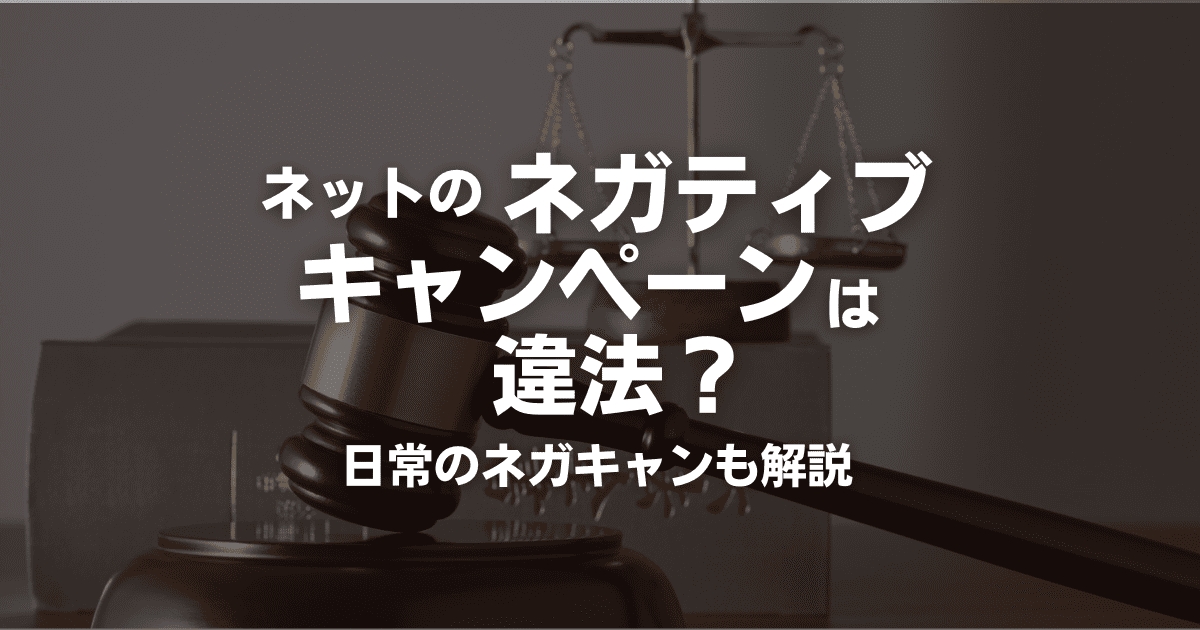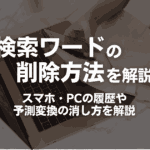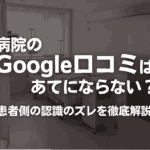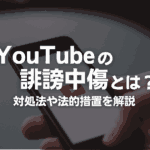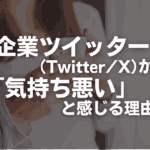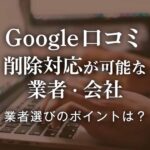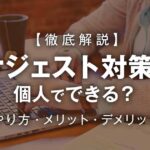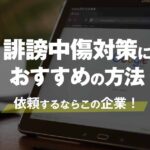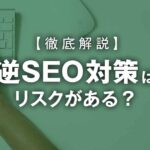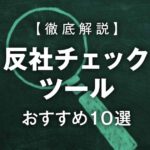ネットでよく目にする言葉の一つである「ネガティブキャンペーン(ネガキャン)」。
話題になっているニュースや口コミを読んでいると、いつの間にか自分もネガキャンの影響を受けている場合もあります。
この記事では、そんなネット上で起こるネガティブキャンペーンについて解説します。
誹謗中傷との違いや、日常生活で使われる若者言葉としての「ネガキャン」なども説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。
▼「好き嫌い.com」の誹謗中傷についても、あわせてチェック!
好き嫌い.comの誹謗中傷対策|コメントの削除方法も解説
目次
ネットで起こるネガティブキャンペーンとは?

ネガティブキャンペーン(ネガキャン)とは、政治・広告・ビジネスなどの競争において相手や競合の評判を下げるために、意図的に否定的な情報を発信する戦略のことです。
分かりやすく説明すると、相手の評価を下げることで自分の評価を上げるという、一種のマーケティング手法と言えます。
そのためネット上で広告・宣伝する際は、日頃から競合によるネガティブキャンペーンに注意しなければいけません。
そしてネットを利用するユーザーもまた、ネガティブキャンペーンによって情報操作されないように気を付けるべきでしょう。
▼ネットの風評被害についても、あわせてチェック!
個人の風評被害は自分で解決できる?事例・影響・対策を徹底解説!
ネガティブキャンペーンに多いのは政治関連
ネガティブキャンペーンが行なわれる例として一番多いのは、選挙をはじめとした政治関連。
具体的な事例としては、選挙運動期間に対立候補の過去の失言やスキャンダル、政策の欠点などがネットに投稿されたりします。
選挙で投票先に悩んでいる際はこういった情報を参考にする人が多いので、その影響は非常に大きいものだと言えるでしょう。
また選挙の場合は、候補者を応援する人たちによって大規模なネガティブキャンペーンが行なわれやすいのも大きな特徴。
場合によっては虚偽の情報によって悪評が広まってしまうこともあるため、ネットでの選挙運動では風評被害にも充分注意すべきです。
ネタとしてのネガティブキャンペーン
広告やビジネスにおけるネガティブキャンペーンでは、わざと競合を煽るような宣伝手法がネタ扱いされているケースもあります。
なかでも有名なのは、ハンバーガーチェーンの「バーガーキング」。
同じくハンバーガーチェーンの「マクドナルド」をイジるような広告は、ネットでもよく話題になっています。
ただし攻撃的な挑発広告に関しては問題視する声もあり、場合によっては炎上マーケティングと判断される可能性がありそうです。
ネガティブキャンペーンの類似語
広告やビジネスシーンにおけるマーケティング用語では、ネガティブキャンペーンによく似た言葉があります。
ニュアンスが若干異なる部分があるので、混同しないように覚えておきましょう。
ネガティブアド(ネガティブ広告)
競合企業や他社製品の欠点などを大げさに取り上げて、見た人にマイナスイメージを与える広告手法です。
自社製品と他社製品を比較する方法で宣伝する場合が多いため、「コンパリソンアド(比較広告)」と呼ばれることもあります。
ネガティブキャンペーン(戦略)のうちの広告表現の一つであるため、ネガキャンとしてまとめられることも多いようです。
ネガティブアプローチ
一般的な商品のマイナス面を伝えて、自社商品でそれを解決できることをアピールするマーケティング手法です。
他社商品を直接的に非難しているわけではありませんが、市場に出回っている商品の不便性を全面に出すというネガティブ要素を含んでいます。
自分の顧客に向けて自社の優位性を伝えることに重点を置いているため、他社を陥れる意図はない点が大きな特徴と言えます。
ネット上のネガティブキャンペーンの違法性

次に、ネット上で起こるネガティブキャンペーンの違法性について解説します。
ネットの匿名性や拡散性の高さから法的な問題に発展しやすい面があるため、それをふまえて理解しておきましょう。
ネットでのネガキャンによるリスク
ネットでのネガティブキャンペーンによる主なリスクは、以下の通りです。
名誉毀損
事実か虚偽かを問わず、相手の社会的評価を低下させる行為は、名誉毀損となります。
また、真実であったとしても公共性がないと判断されれば、名誉毀損が成立する場合もあるようです。
プライバシーの侵害
相手の私生活や個人情報を暴露した場合は、プライバシーの侵害となります。
主に相手のプライベートな問題をSNSで広めたり、住所や家族構成を無断で公開したりする行為が該当しますが、名誉毀損にも抵触するでしょう。
著作権の侵害
相手の創作物(音楽・映像・写真・イラスト・文章)を無断で使用すると、著作権の侵害となります。
競合他社の商標や広告画像を勝手に使って批判的な内容で発信すれば、損害賠償が発生するような大きな罪に問われることは間違いありません。
その他
ネガティブキャンペーンによって競合他社の商品やサービスの評判を損なわせて販売を妨害した場合は、独占禁止法や不正競争防止法に違反する可能性があります。
また、虚偽の情報を流して相手の業務を妨害した場合は、偽計業務妨害罪に問われる恐れもあるでしょう。
このように、ネガティブキャンペーンは相手がうけた被害によって、さまざまな法的な問題に発展することが考えられます。
選挙におけるネガキャンの違法性
政治や選挙活動におけるネガティブキャンペーンは、違法性が問われにくい傾向があります。
なぜなら、政治家や立候補者の活動には公共性・公益性があり、政策や言動に対する批判は国民の「知る権利」に繋がるためです。
したがって、事実に基づいて公共性や公益性が認められる批判であれば、名誉毀損罪などの違法行為に該当しません。
ただし、明らかに虚偽の事実を広めて当選を妨害した場合は、公職選挙法違反(虚偽事項公表罪)として法的責任を問われる可能性があります。
総務省|インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要|(2) 誹謗中傷・なりすまし対策等|1 誹謗中傷・なりすまし対策
<氏名等の虚偽表示罪の改正>
氏名等の虚偽表示罪(公職選挙法第235条の5)の対象に、インターネット等による通信が追加されます。
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称又は身分を表示してインターネット等を利用する方法により通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされ(改正公職選挙法第235条の5)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
<虚偽事項の公表に関する既存の刑罰>
(虚偽事項公表罪)
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
(名誉棄損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。
なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。
禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。
(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされています(刑法第231条)。
ネットのネガティブキャンペーンと誹謗中傷の違い
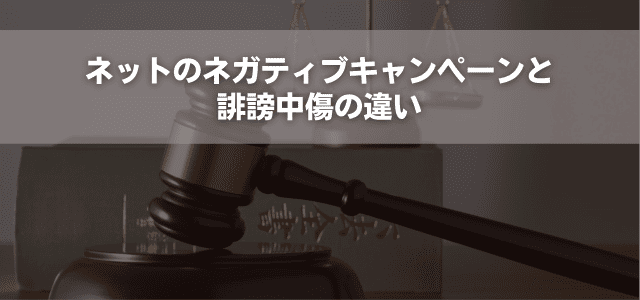
ここでは、ネガティブキャンペーンと誹謗中傷の違いを説明します。
どちらも否定的な情報を発信して相手の評価を下げる行為ですが、明確に異なる点があるのでしっかりと理解しておきましょう。
▼ネットの誹謗中傷については、こちらで詳しく解説しています。
ネットの誹謗中傷を検索してチェック!対処法も解説
事実に基づくネガキャンも多い
ネガティブキャンペーンは、競争上の優位性を確立するために、事実に基づいた発信を行なうのが基本です。
自分や自社を有利にすることを目的とした戦略的な情報発信であるからこそ、事実を示すことでその効果が発揮されます。
それに対して誹謗中傷は、相手の人格や名誉を傷つけることが目的です。
事実に基づくかどうかに関係なく、根拠のない悪口や不確かな情報、感情的な罵倒によって相手を貶める点で非常に悪質と言えるでしょう。
誹謗中傷の方が違法になる可能性が高い
誹謗中傷は個人の感情に基づく攻撃的な行為であるため、法的な責任を問われる可能性が高いです。
具体的には、名誉毀損やプライバシーの侵害に該当する恐れがあります。
そのため、自分では合法的なネガティブキャンペーンのつもりが、誹謗中傷になってしまっていたという例も珍しくありません。
感情的になってしまうと相手を傷つけることが目的になってしまいがちなので、法的な責任の境界線をしっかりと意識するべきでしょう。
ネガキャンが誹謗中傷になるラインとは?
明らかに虚偽の事実を捏造・流布している場合は、誹謗中傷になります。
逆に言えば、「事実が真実である」もしくは「真実と信じるに足る客観的な根拠がある」のであれば、合法的なネガティブキャンペーンと言えるでしょう。
しかし、ネガティブキャンペーン自体にリスクがあることは変わりありません。
公共性・公益性のある情報であれば違法ではないとはいえ、相手に被害を与えてしまえば罪が成立してしまうことを覚えておいてください。
ネガティブキャンペーンとネガキャンの違い

ネガキャンはネガティブキャンペーンの略称ですが、日常生活で使われる「ネガキャン」はニュアンスが異なります。
特に近年では若者言葉のイメージが強い人も多いので、その違いを理解しておきましょう。
▼Vtuberへの誹謗中傷についても、あわせてチェック!
Vtuberへの誹謗中傷や暴言は罪になる?誹謗中傷された時の対策も解説
日常のネガキャン=ディスる
日常的に使われる「ネガキャン」は、特定の相手に対する不満や悪意の発散など、個人的な目的で貶める行為を指します。
具体的には、単に「あの人が悪口を言っている」「あの人を批判している」といった個人間の陰口や批判の流布であることが多いです。
そのため、相手を軽蔑・侮辱する「ディスる」と同じ意味で使われます。
学校や職場で起こるネガキャンの特徴
学校や職場で発生するネガキャンは、嫉妬や過去のトラブル、気に入らないといった個人的な感情が動機となることが多いです。
したがって、エスカレートするといじめやハラスメントと見なされるのが特徴。
倫理的な問題だけでなく、法的な問題に発展するリスクも高いため、組織内でのネガキャン行為を放置するのはとても危険です。
ネットで誹謗中傷されている可能性も
学校や職場でネガキャンを行なう人は、SNSなどのネットで誹謗中傷をしている可能性が非常に高いです。
対面での陰口や噂話ではネガキャンの範囲でも、ネットでは誹謗中傷に発展しているケースは珍しくありません。
それゆえに、身近にネガキャンをしている人がいる場合は、自分を含めて周りの人が誹謗中傷の被害に遭っている恐れがあります。
ネットで誹謗中傷に遭ったらBLITZ Marketingにご相談ください

「BLITZ Marketing(ブリッツマーケティング)」では、ネット上に投稿された悪質な誹謗中傷・風評被害を早急に解決することができます。
24時間体制で受付しているため即日着手できるので、掲示板・ブログ・口コミ・SNSなどに投稿されたコメントにお困りの場合はぜひお任せください!
また、BLITZ MarketingではGoogleなどの検索エンジンに検索窓に予測表示される「ネガティブワード」や、検索結果の上位に表示される「ネガティブ記事」など、あらゆる要素をまとめて対処することが可能です。
もしネット炎上を引き起こしている状態であれば、そういった被害もあわせて対処することで、できるだけ早く事態を鎮静化させられます。
今ならお問い合わせ頂いた方に、リスク調査シートを無料で作成!
検索結果・サジェストに表示されるネガティブ状況を専門スタッフが網羅的に調査するので、この機会にネットのリスクをチェックしてみませんか?
相談は無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
\誹謗中傷・風評被害対策なら/
【まとめ】ネットのネガティブキャンペーンは誹謗中傷に注意!
ネット起こるネガティブキャンペーンは主に選挙などの政治関連であり、公共性・公益性のある情報を発信しています。
なかには広告やビジネス関連もありますが、いずれも事実に基づいた情報発信を行なうのが基本です。
しかしその一方で、日常的に起こるネガキャンは個人的な感情で相手を傷つける行為を指すことが多いのが特徴。
いじめやハラスメントとして扱われ、誹謗中傷に発展する可能性が高いので、ネガキャンが身近で行なわれている場合は注意しましょう。
投稿者プロフィール

- 誹謗中傷対策とWebマーケティングに精通した専門家です。デジタルリスク対策の実績を持ち、これまでに1,000社を超えるクライアントのWebブランディング課題を解決してきました。豊富な経験と専門知識を活かし、クライアントのビジネス成功に貢献しています。
最新の投稿
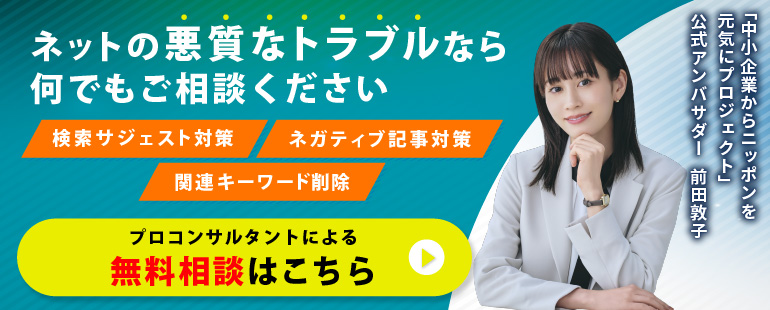
\ かんたん30秒で無料相談 /
お問い合わせはこちら